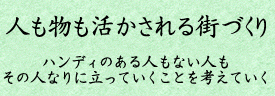「40年間を振り返る・・少し長めの代表のつぶやき」
R7.1.26
(特非)太陽と緑の会代表理事 杉浦良
太陽と緑の会は1984年8月から「人も物も活かされる街づくり」をスローガンに、様々なハンディーを抱えたメンバーと、リユース・リサイクル活動を始めました。
使われなくなった徳島市入田町月ノ宮の豚舎を使えるようにするため、第1関門が背丈ほどの雑草との格闘、第2関門は水の確保とトイレの確保、ぬかるむ進入路の舗装や軒工事、電話の開設など、そして第3関門は不用品回収や広報宣伝、次に第4関門はメンバーの確保、最後に運営費の捻出という、第5関門が待ち受けていました。
スタートから2か月後、買取りも処分料も頂かない、不用品回収活動を行い、その2か月後、徳島市にある近藤整形外科駐車場をお借りして、ガレージセールを行うことができました。20万円ほどの売り上げに、喜んだのはもちろん、以後毎月第4日曜日の、リサイクルバザーとして、続けることができたのは、太陽と緑の会の創立者、近藤文雄と奥様、そしてボランティアの皆さんのお陰です。
太陽と緑の会は1971年、昭和46年4月に徳島市で設立されました。仙台にある国立西多賀病院院長を辞職し、郷里の徳島に戻った整形外科医近藤文雄が、筋ジストロフィー研究所設立運動を始める団体として作ったものです。国立西多賀病院の筋ジス病棟を舞台にした、福祉ドキュメンタリー映画「僕のなかの夜と朝」を近藤文雄は携えてきました。
徳島県内で上映会を開き、城北高校の体育館でも上映され、それを見た高校生たちが長年ボランティアとして関わってくれました。会の活動が広がり、25万人もの署名を集め、国会請願するに至った経緯や、最終的には武蔵野神経センターに落着いたいきさつ、そしてその後、ボランティア活動推進に切り替えた一連の流れは、近藤文雄著「先生、ぼくの病気いつ治るの」(1996年中央公論社)に書かれています。また近藤文雄の考えや価値観をまとめた「私の世界観」(近藤文雄著1995年)があります。
そんな下地があったことで「太陽と緑の会リサイクル」は第1関門、第2関門、第3関門、第4関門を何とか乗り越えられたと思います。第5関門については、随分苦戦してきました。1986年には徳島県で初めての障害者小規模通所作業所(無認可作業所)として公的補助金を年間130万円頂けるようになりました。ただ運営費の8割以上は、自力で捻出しなくてはなりません。社会保険・厚生年金に加入できたのがスタートから12年後、そして年間300日、夜なべ作業が当たり前の長時間労働を、30年間続けてきました。今から振り返ると、ワーカーホリック・仕事中毒的活動でした。ただボランティアの皆さんも、仕事以外の空いた時間で支えてくれているわけですから、当然のことだったわけです。働き方改革の今では、想像できないかもしれません。
1986年、徳島市が新庁舎建設のために、仮事務所として使っていたプレハブ2階建てを無償で頂き、現在の徳島市国府町南岩延に、県建設業組合の皆さんが、無償で移築して下さいました。土地は当時の笠井穆・笠井仏壇社長から、払えるだけの地代でいいからと、200坪を貸して頂きました。続けられた背景には、そんな有難いサポートがありました。
当たり前のことですが、ボランティアの支えだけでは運営できません。様々なハンディーを抱えたメンバー達も、やれることはやってくれますが、やれない多くの部分は、専任スタッフがやらなくてはなりません。3K4Kとか言われてしまうこの活動を、担ってくれる人の確保が急務です。そのためにも専任スタッフ給料確保に、古紙や鉄屑といった資源リサイクル収入以外の、家具や電化製品、雑貨や衣類、自転車など、ありとあらゆるものを分別整理、修理再生し、常設店販売で運営費を捻出する必要がありました。徳島で最初のリサイクルショップを立ち上げましたが、前例がないということの大変さは、想像を絶するものがありした。
何とか70坪2階建ての店舗兼作業所兼事務所兼生活棟が確保できました。ただ専任スタッフ確保は難しい状況が続きました。そんな時、日本青年奉仕協会の1年間ボランティアの話がありました。全国各地にある福祉、教育、環境、文化事業等の活動先に、全国からの若者を1年間派遣し、お互い実りある事業として、展開していました。海外青年協力隊の国内版ともいえる事業でした。長野出身の荒川君が、1988年4月、当会初めての1年間ボランティアとして参加してくれました。以来、日本青年奉仕協会が解散する2009年まで、23人の若者が、当会に関わってくれたことが、継続の原動力となりました。
1990年9月から10年間続けたワークキャンプ事業は、月の宮夢構想を実現するための、大きな起爆剤になりました。アジアボランティアの受入れなど、日本青年奉仕協会との関係は、大きな意味がありました。
2005年2月27日(日)午前5時前、1階入口付近より出火した火災により、大きなダメージを受けました。幸いケガ人も延焼なく、奥にある作業倉庫を借りていたお陰で、4日後には活動を再開でき、その後の再建への流れとなりました。
5000人もの支援を頂けたこと、火災保険金が下りたこと、そして元木内工務店社長・木内昭さんの献身的な支援を得られたことで、前と同じ70坪2階建の新館が、1年後に完成しました。それは奇跡と言えるものでした。
ただその3年後、日本青年奉仕協会は解散することになります。全国各地からの若者が来なくなり、少子高齢化の波も押し寄せ、そのことは、会の閉塞感に繋がりました。ボランティア募集サイトにも反応がなく、今後の展望が見えなくなりました。
それを打開してくれたのが、定年退職された高齢者パワーです。メンバー達への対応も大きく変わってきます。
「それは、世間では通用せんよ」といった指摘や「ここに来て自分も随分気が長くなった」といった言葉は、別の広がりを持ちます。
40年も続けているとメンバーやボランティアにも大きな変化がありました。1998年3月11日に近藤文雄が、翌年に柳澤寿男が、その10年後に笠井穆社長、その2年後に新館建設立役者である、木内昭さんも旅立ちました。そういう私も古希を迎えての活動となりました。
40年前にはリサイクルショップという言葉自体がなかったですが、徳島で最初のリサイクルショップも、今ではどこにでもあり、高価買取りを謳っています。買い取れるものは買取り、そうでないものは処分料をもらう。それが普通のビジネス時代となりました。ネット販売が当たり前となり、値段設定に労力を投入するだけでなく、ディスプレイや盗難対策が必要となりました。処分するコストも高くなり、鉄屑としてそのまま資源化できた電化製品や自転車も、解体分別しなければ納入できません。昔、徳島市はドラム缶焼却炉の無料提供で、ゴミの減量推進をしていましたが、今では小さな焼却炉にも2重扉や助燃バーナー、送風機設置が義務付けられました。処理するハードルがどんどん上がり、処分コストが増大しました。
大きく変わる時代の中で、相変わらず愚直に、無料引き取りで、リユース・リサイクル活動を続けています。3障害のメンバーを受け入れ、個別給付事業には移行せず、公的資金を受けずに生活棟も運営しています。
40年前には、障害者は身体障害と知的障害の2つだけでした。ですから3障害のメンバー受け入れという言葉は、厳密にいえばウソとなります。精神障害という言葉はなく、障害者福祉の中には精神障害者はいませんでしたし、発達障害という言葉もありません。パソコン自体がなく身体障害の方の仕事エリアは、狭く厳しいものでした。そんな中で徳島県最初の福祉共働作業所をスタートしました。2003年には、無認可作業所は全国で6000ヵ所にもなりました。2006年の障害者自立支援法制定後、大部分は公的資金が多く獲得できる、就労継続支援事業所に移行しました。身体・知的・精神・難病・発達障害まで障害福祉のエリアは拡がりました。一般事業所からの参入も多くなり、現在はビジネスモデルとしての障害者福祉が、目立つようになりました。
自宅待機で、通える学校がない時代から、養護学校を出ても、通える作業所がない時代に、そして今は、障害者獲得の時代になったと言えるでしょう。
「割に合わない活動」から、「割に合う事業」への移行と言えば、不謹慎でしょうか。
「基本的人権の尊重」といった軸より、「慈愛」や「慈悲」での軸、そして「社会運動」としての障害者福祉の歴史を、私は見てきました。
また、無意識に継承された偏見や差別は、奥底では、自分も含めて、そう変わるものではない、そう思う私があります。
いつの間にか、1300兆円近くの赤字を抱えた日本は、税収入で予算を組める国ではなくなりました。赤字国債を発行することでかろうじて社会保障が成り立つ今、少子高齢化が進み、格差が広がる中で、成熟社会、持続可能社会に移行せざるおえなくなりました。善良な人が損をすることなく、色々な立場の人たちが、それなりに暮らしやすい社会の在り方の模索が重要課題となりました。
理想的な障害者福祉の在り方に、桃源郷的な世界を求める歴史がありました。ただ私が知る限り上手くいった事例を知りません。QOLを高めることが、障害者福祉の重要課題だとも、もう思えません。辛くて厳しい今の社会から離れて、桃源郷を求めたり、薔薇色の障害者福祉を模索したい気持ちも分かります。ただ現実社会と切り離して、障害者福祉のみが自律的に成り立つ筈はありません。
リユース・リサイクル活動から見えてくる世間があります。当たり前のことですが、今お金にならないもの、その時必要とされないものが、ここ太陽と緑の会に集まってきます。
しかし、他のリサイクルショップで引き取らないものを、当会に持ち込むのが当たり前の時代に、十分買い取っていただける品物を提供して下さる、心ある方の存在があります。また掘り出し物を探される方以外に、厳しい生活環境で暮らしておられるだろう人達の姿にも出会います。
「ここがないと本当に困る」そんな言葉に背筋がピンと伸びるだけでなく、必要とされていることの有難さを感じます。
「福祉とは底辺に向かう志」と語った小倉襄二氏の言葉が光り輝きます。
「世間の風が強すぎると、自分の足で立てなくなるが、あまりにも囲い過ぎると、世間では生きられなくなる・・」そんなことを想いながらこの活動をスタートしました。40年経って、ますます先が見えない時代になりました。ただ40年経った今も、スタートしたその想いは変わらず、むしろ強くなったと感じます。そして今でも相変わらず、公的支援に頼らず、運営費の8割は、皆様の協力を頂きながら、スタッフ・ボランティア、そして様々なハンディーを抱えたメンバーが頑張ることで、ここを成り立たせています。